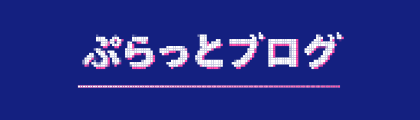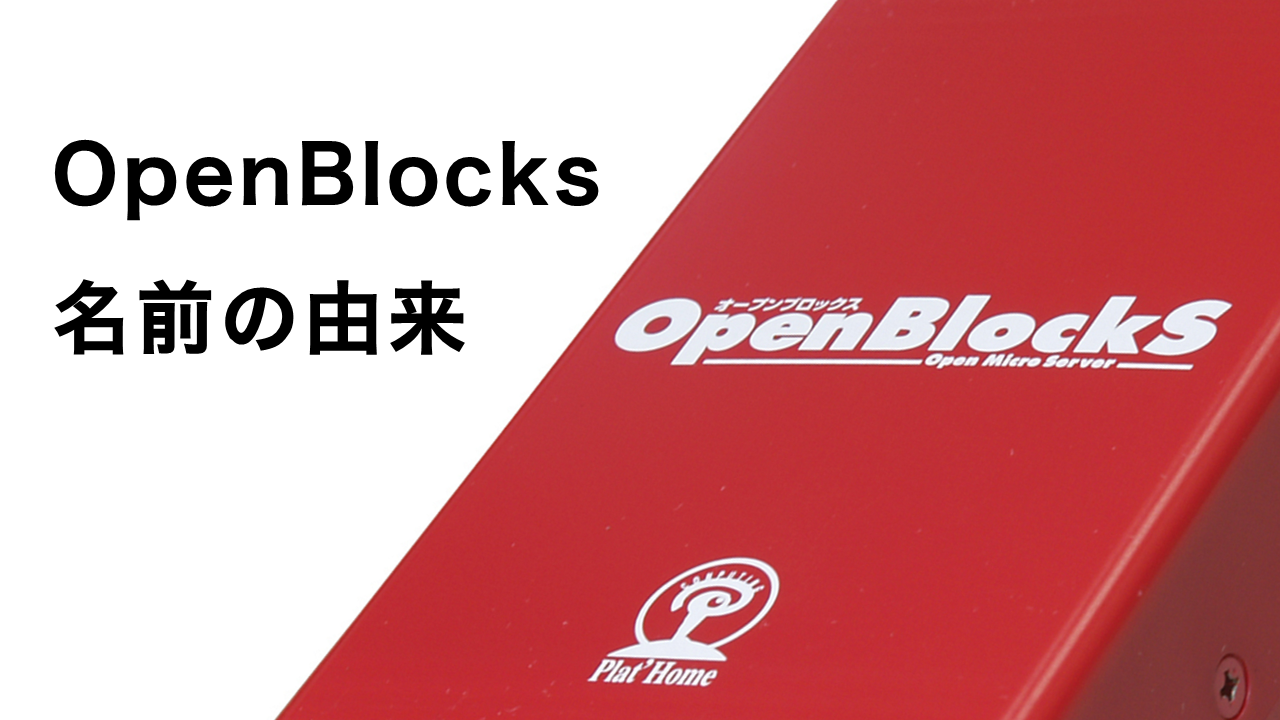「ぷらっとホームといえばOpenBlocks」・・・とまでは言わないですが、当社の製品名の中では一番知名度が高いんじゃないかと思います。お客さんの中でも「あー、あの小さいLinuxサーバーでしょ?」とすぐに思い浮かべてくれる方が多い印象です。
でもその名前の意味まで知ってる人って、実はそんなに多くないんじゃないかと思いまして。
今さらですが、今回はそんなOpenBlocksシリーズの、名前の由来と、歴代モデルに込められた意味をまとめてご紹介してみます!
初代:OpenBlockS

OpenBlocksの始まりはここから。このときはなぜか最後のSだけ大文字で、「OpenBlockS」という表記でした。
- Open Source Software を動かすための Block(=装置) にしたい
- BoxじゃなくてBlockなのは、LEGOとかダイヤブロックみたいに遊んでほしかったから
- そして最後の「S」は、複数形ではなく Serverの“S”
という、当時のこだわりが詰まった命名だったそうです。
「おもちゃみたいに自由に使っていいよ」っていうノリがちょっとかわいいですね。
OpenBlockSS

読み方は「オープンブロックス・エス」。末尾の「S」は、SuperとかSecondとか、いろんな意味が込められていたっぽいですが、正直なところ、ここは諸説あります(笑)
OpenBlockSR

こちらは読み方はオープンブロックス・アール。Renewalの“R”かな・・・?と思いきや、ラックマウント(Rackmount)対応の”R”だそうな。もともとはコンシューマ寄りの製品でしたが、徐々に法人でも使われ出してきてサーバーラックへしっかりと取り付けたいという要望に応えた製品だそうです。

OpenBlockS 266 / OpenBlocksS 600

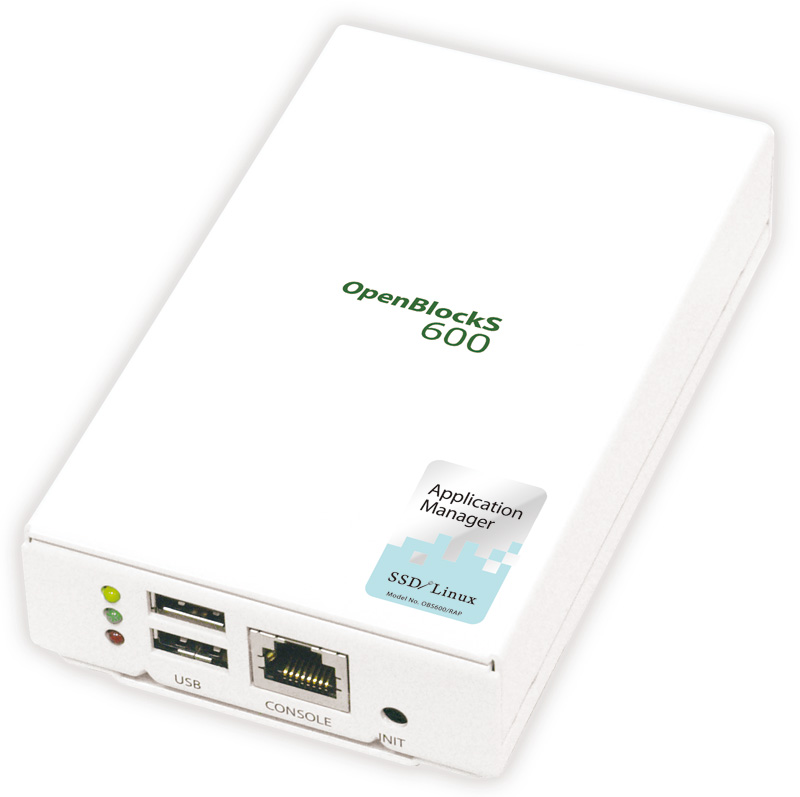
このあたりはストレート。
- OpenBlockS 266:PowerPC 405GPr、266MHz搭載
- OpenBlocksS 600:PowerPC 405EX、600MHz搭載
クロック数をそのまま名前にしてるだけです。潔い。
ちなみに私は、このOpenBlockS 600が出た2009年に入社したんですが、
途中で製品名の「OpenBlockS」が「OpenBlocks」(末尾が小文字に)に変わりました。
理由はというと……
「オープンブロックエス」って読んじゃう人が結構多かったので、うちの社員とお客さんの呼称のズレをなくしたかったから、とのこと。
OpenBlocks AX3 / OpenBlocks A6


ここからARMアーキテクチャCPUを採用しはじめました。
- OpenBlocks AX3:1.3GHz デュアルコア
- OpenBlocks A6:600MHz シングルコア
実はこの2機種、元の名前案はそれぞれ:
- AR X-1300
- AR 600
・・・だったんですが、名前が長すぎるわ!ってことでボツになりました。
最終的には、ARMの”A”と、数字をうまく縮めた「AX3」「A6」に落ち着いたという経緯です。
ちなみにこのとき、歴代OpenBlocksの中で、唯一私が出した名前案が採用されたモデルなので、今でもちょっと特別な思い入れがあります。
OpenBlocks A7

A6の後継機。Ethernetポートが1つ→2つに増えたモデル。
命名の理由はとてもシンプルで
「A6の次だからA7でいいよね?」
というノリだったと記憶しています。うん、まあ、わかりやすいですがちょっと一貫性がなくなってきましたね・・・?
OpenBlocks IX9

ここでついにインテルアーキテクチャモデルが登場!
- “I”:Intelの”I”
- “X9″:1.9GHz(=19)を表したもの
I × 19 = IX9、というちょっと語感重視な感じもあります。
OpenBlocks HX1

2025年現在のOpenBlocksフラッグシップモデルで、こちらもIntelアーキテクチャ採用ですが、頭文字が「I」じゃなくて「H」なのが特徴。これはHigh GradeのHという意味が込められているそうな。
まとめ
というわけで、OpenBlocksの名前の由来を一気に振り返ってみました。製品の性能だけじゃなく、名前にもちゃんと意味があるんだな〜と改めて思うきっかけになればうれしいです。「OpenBlocksってそういう意味だったんだ!」みたいな小ネタとして、誰かの記憶に残ってくれたら、それだけで満足です。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
ちなみに、歴代モデルの詳細は以前、清水がブログでまとめているのでぜひそちらもご覧ください。